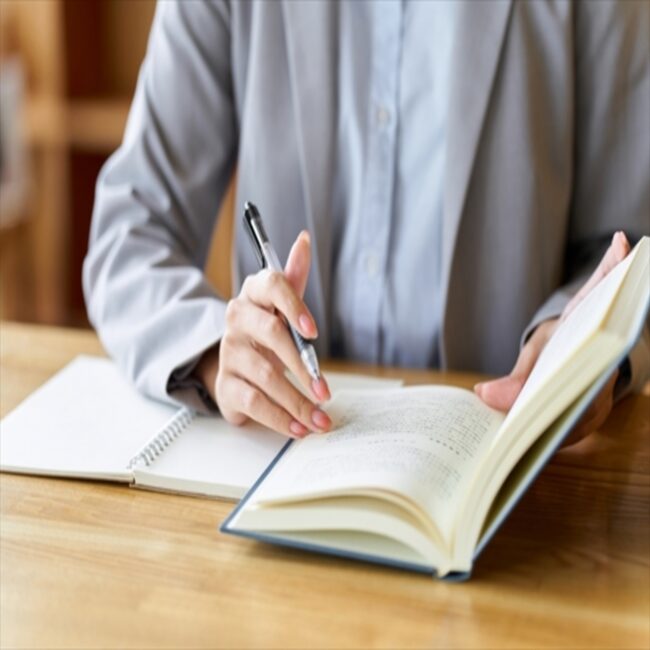オフィス家具
全く同じ家具だらけの時代は終わり?”あえてバラけさせる”オフィスのススメ
「全部、同じ椅子」「全部、同じ机」。 オフィス家具って、なぜあんなに“揃っている”んでしょう? それが「普通」だった時代は、もう終わりを迎えようとしています。 今、注目されているのは、あえて“バラけさせる”オフィス家具配置。 統一感は保ちながら、選ぶ楽しさと自由さを加える。 今回はそんな、新しいオフィス空間のあり方をご紹介します。
1.なぜ「全部同じ」が当たり前だったのか?(従来の背景)
「オフィス家具=揃えるもの」。そんな常識が長く根づいてきた背景には、いくつかの理由があります。
まず、同じ家具をまとめて導入すればコストを抑えやすく、在庫やメンテナンスの管理もシンプルになります。
さらに、「全員同じ」という見た目は、社員に対して“平等な環境である”という安心感を与える効果もありました。
とくに日本では、机を向かい合わせに配置する「島型レイアウト」が長く主流でした。
これは限られたスペースで大人数が働けるようにするもので、上司の目も届きやすいことから、組織運営に適したスタイルとされてきたのです。
その中で「同じ家具・同じレイアウトで整え、座る位置だけで序列を示す」という文化が、自然に根づいていきました。
2.それでも今“バラけたオフィス”が選ばれる理由
今、働き方も価値観も“均一”ではありません。
集中したい時もあれば、気分転換が必要な日もあります。
チームで議論したい日もあれば、一人でじっくり考えたい日もある──そういう変化に対して、毎日同じ椅子・同じ机の環境だけでは、逆に窮屈に感じることもあるでしょう。
そこで注目されているのが、Activity‑Based Working(ABW)という働き方です。
これは「社員が業務内容や目的に合わせて、働く場所や時間を選べるオフィス」を設計する手法で、日本でも導入事例が増えています。
実際に、株式会社イトーキが実施した調査では、ABW導入後、社員の「生産性が高いと実感している」割合が、導入前の32.4%から77.0%へと大きく向上したという結果が報告されています
[出典:イトーキ公式サイト|https://www.itoki.jp/resources/column/article/achievements-and-challenges/]。
固定席に縛られない自由。選べることが、働く人の意欲やパフォーマンスを高めてくれる時代なのです。
3.「バラバラでも整って見える」秘密
「あえて家具をバラバラにするなんて、雑然としない?」
そう思う方も多いかもしれません。
でも、実は“整って見えるバラつき”をつくる工夫があります。
それは、家具そのものではなく、空間全体の“見え方”を整えるという考え方です。
たとえば、素材や色味をゆるやかに統一する方法。
木目×黒脚など、質感やトーンをそろえることで、見た目にまとまりが出ます。
また、家具の高さや奥行きを揃えることで、視線のラインが整い、自然と秩序を感じさせることができます。
さらに、「集中ゾーン」「会議ゾーン」「休憩ゾーン」などのゾーニングを行うことで、用途ごとのまとまりが生まれます。
異なる家具が並んでいても、「その場所にはその家具がふさわしい」という納得感が空間に生まれるのです。
加えて、最近は“色をあえてバラす”手法にも注目が集まっています。
とはいえ、ただ派手な色を散らすのではなく、色数をしぼる・色を繰り返すといったテクニックを使えば、
色の違いさえも「統一感」の一部に変えることができます。
こうした“空間の見え方”を意識すれば、バラバラな家具でも、洗練された印象をつくることができるのです。
4.「あえて崩す」家具選び、成功のための3つのポイント
空間全体の見せ方を工夫する一方で、家具選びの段階でも“崩しすぎない”工夫が大切です。
個性と統一感を両立させるための3つのポイントをご紹介します。
① ベースを揃えて、アクセントで遊ぶ
すべてを変える必要はありません。メインの家具は共通仕様にしつつ、一部に変化を加えることで、全体の秩序を保ちながら、ちょうどよく“ハズし”を加えることができます。
たとえば、執務スペースのデスクや収納は統一し、チェアだけ複数のタイプを混ぜてみる。
あるいは、会議エリアの椅子や、リラックススペースのスツールにアクセントカラーを取り入れると、空間にメリハリとリズムが生まれます。
重要なのは、「すべてをバラバラにする」のではなく、統一感の中に“ちょっとした違い”を組み込むこと。
これにより、“整って見えるバラつき”が演出できるのです。
② 「役割の違い」で見た目を変える
オフィスには、集中・リフレッシュ・コミュニケーションなど、さまざまな機能が求められます。
空間の“用途”に応じて家具の見た目を変えることで、バリエーションに意味を持たせることができます。
たとえば、
執務エリア:落ち着いたトーンで統一
リフレッシュエリア:明るい色や柔らかい形状の家具を配置
といった工夫で、バラけた家具配置にも“意図”が感じられるようになります。
③ 色の“選び方”にルールを持つ
色で遊ぶ際も、無秩序に増やさないことが空間のまとまりにつながります。
空間の色選びにおいて基本バランスに「7:2.5:0.5の法則」があります。
これは空間に使う色の割合として、
ベースカラー(約70%):床や壁、大型家具など、空間全体を支える色
メインカラー(約25%):チェアやデスクなど、印象を決める主役の色
アクセントカラー(約5%):スツールや小物など、差し色となる装飾的な色
に分類して考える方法です。
この法則を応用すれば、複数の色を使っても視覚的に整った印象をつくりやすくなります。
参考:RECENO|カラーコーディネートの基本 (https://www.receno.com/pen/coordinate/u64/2024-08-07.php)
さらに、以下のような工夫も効果的です:
色数を限定する:3〜4色程度に絞ると、ごちゃつきを防げる
色を繰り返す:同じ色を複数の家具に使うと、視覚的なリンクが生まれる
中立トーンを軸にする:グレー、ナチュラルウッド、白などの“なじむ色”を基盤にすれば、アクセントカラーが際立ちすぎず調和しやすい
5.統一感を崩さずに“遊び”を加える家具選び (おすすめ家具)
色や素材に変化があるチェアを“ひと工夫”で取り入れる
ベースの家具を揃えながら、一部にだけ素材や色味の異なるチェアを取り入れると、空間に自然な変化が生まれます。使う場所や目的に応じて、次のようなアイテムを組み合わせるのも一つの方法です。
ワンカラーミーティングチェア:商品ページ

座面から脚まで同色で仕上げられた、ミニマルなデザインのチェア。カラーによって雰囲気が変わるため、会議スペースや共有スペースに取り入れると、場の空気が少しやわらぎ、アイデアの出やすい雰囲気づくりにもつながります。スタッキングも可能で、使い勝手にも配慮されています。
※当社の会議室にも使用されています。
シースルーチェア:商品ページ


透け感のある素材とカラーバリエーションが特徴。同じ執務スペース内でも、あえて数脚だけ色を変えて配置することで、硬くなりがちな空間にほどよいアクセントを加えることができます。視覚的にも動きが生まれ、印象が単調になりません。
オーロラチェア:商品ページ

やわらかい色味と曲線のフォルムが特徴のチェア。デザイン性が高いため、執務スペースはもちろんですが、共有スペースや来客スペースなど、目に留まりやすい場所に取り入れることで空間全体が明るい印象になります。1脚だけでもアクセントとして十分に効果を発揮します。
このようなアクセント家具は、取り入れる場所と数を絞ることで“遊び”として機能しやすくなります。ベースの家具と調和する範囲で選ぶことで、空間全体に統一感を持たせつつ、印象的な演出が可能です。
6.まとめ
これまで当たり前だった「全て同じ」オフィス家具のスタイルも、今の働き方には必ずしも合わない場面が増えてきました。
使う人や目的に合わせて少しずつ変化をつけることで、働く環境に柔軟さや心地よさが生まれます。
大きく崩す必要はなく、素材や色味を揃えながら“違い”を取り入れることがポイントです。
ちょっとした工夫で、統一感を保ちながら、使いやすく印象に残る空間をつくることができます。
まずは、空間の一部にアクセントとなる家具を取り入れてみませんか?